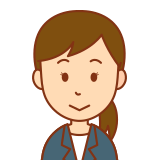
精一杯授業をしているんですが、なかなか学習者からの発話が引き出せません。
新人の頃って「ちゃんと説明しなきゃ!」と思いがちですよね。
でも実はそれ、大きな落とし穴なんです。
学習者が説明を聞いて「なるほど」と思っても、そのままでは使えるようになりません。
サッカーのルールをよく知っていても、ボールを蹴った経験がなければ試合で活躍できないのと同じで、頭で分かっていることと実際に口から日本語が出てくることの間には、大きなギャップがあります。

日本語も「やってみる」経験を通して初めて身につき、使えるようになります。
だからこそ授業では「説明は短く、体験は長く」という意識が大切になると思います。
そこで今回は「体験型授業・学習者参加型授業」を作っていくヒントを紹介したいと思います。
これから日本語教師デビューを迎える人や、授業の進め方に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
✔️授業中についつい長々説明してしまう
✔️学習者参加型授業の進め方がわからない
✔️どんな活動を取り入れればいいのかわからない
✔️参加型授業がうまくいかない
1. なぜ「説明」より「体験」が大事なのか

日本語の授業では、教師が文法表現や語彙を説明する場面がよくありますが、「分かる」のと「使える」のは全く別です。
学習者が説明を聞いて、大きく頷いて、その場では理解したように見えても、実際の場面でその表現が口から出てこなければ、あまり意味がありません。
言語はスポーツや楽器の練習に近いものです。
頭で理屈を知っているだけでは身につきません。
日本語学習も「体験」の中で繰り返し口を動かし、試行錯誤することで初めて使える力になります。
また、体験は感情と結びつくため、記憶に残りやすいという利点もあります。
「楽しかった」「できた」「失敗して悔しかった」などの感情と結びつくことで、体験は学習を継続する原動力になります。

一方、教師が長く説明をしてしまうと、学習者は受け身になり、集中力が切れてしまうことも少なくありません。
だから、私は「説明を最小限にして、できるだけ体験の時間を増やす」ことを意識して授業をしています。
教師は説明者ではなく、学習者が日本語を実際に使える場をデザインしたり、学習者をサポートしたりする存在であるべきだと考えているからです。
2. 参加型授業で大切にすべきこと

「学習者中心の授業ってよく聞くけど、具体的に何をすればいいの?」
と新人のうちは悩みがちだと思いますが、シンプルなコツを4つ紹介します。
1つ目は「説明はコンパクトに、体験はたくさん」
これを意識することです。
5分も10分も長々と説明するより、30秒~1分でポイントを伝えて「やってみよう!」と動かす方が効果的だし、学習者もついて来てくれます。
2つ目は「全員が関われる仕組み」を作ること。
授業中、声の大きい学習者や積極的に発話する人だけが話してしまうと、静かな人は置いていかれてしまいます。それを防ぐために、ペアワークやグループワークを取り入れて、一人ひとりが発話するチャンスを確保しましょう。
3つ目は、「正解よりもやってみることを評価する」雰囲気づくりです。
間違えるのが怖かったり恥ずかしかったりする学習者は、あまり自発的に話してくれません。
でも、教師がチャレンジを評価し、「いいね!言ってみてくれてありがとう」と声をかけ続けていれば、日本語を使おうとしてくれるようになります。
大事なのは「正確さ」よりも「まず口に出すこと」だと継続して伝えてみてください。
最後に意識したいのは、あくまでも「教室の主役は学習者である」ということです。
クラスをコントロールしようとするのではなく、学習者が自分で動きやすいようにサポートすることを心がけてみてください。
授業を「説明の場」から「学習者が体験する場」に変えていくことが、参加型授業を作る第一歩です。
3. 取り入れやすいアクティビティの例

「アクティビティってどうやって考えるんだろう…」
と思う人もいると思いますが、まずは身近な活動から始めていけば十分です。
大事なのは学習者が日本語を使う場面を作ることです。
凝った仕掛けや工夫よりも「すぐできる・すぐ話せる活動」という点を押さえてください。
定番はペアワークです。
質問カードを使ったインタビューや、ロールプレイ形式の会話練習などは準備もそれほど時間がかからず、取り入れやすいです。
ペアで話すと「間違えても目立たない」という安心感があり、学習者も発話しやすくなります。
次におすすめなのはグループワークです。

インフォメーションギャップを使った活動や、ゲーム要素(競争、協力、時間制限)のある活動、グループで何かを作り上げる活動は盛り上がりやすく、自然にコミュニケーションが生まれます。
慣れてきたら、全体活動にもチャレンジしてみてください。
クイズ形式やリレー形式のしりとりなどは、クラス全体を巻き込めるので絆も深まり、クラス全体の雰囲気も良くなります。

また、「今日はこれで終わり!」というときに入れると、楽しく締められます。
どんな活動でも、「小さくても全員が参加できる」ことがポイントです。
アクティビティには完璧を求めすぎず、まずは一つお気に入りを見つけることから始めてみてください。
4. 参加型授業を成功させるコツ

「活動を入れてみたけど、いまいち盛り上がらなかった…」という失敗は誰もが通る道です。
参加型授業を成功させるには、ちょっとした工夫が必要です。
まず一つ目は難易度の設定です。最初は「これなら言える!」というレベルから始めてみましょう。
簡単に言える活動で成功体験を積むことで、学習者は次も挑戦しようと思えます。
その後徐々に難易度を上げて「チャレンジ要素」を加えてみてください。
二つ目は教師の立ち位置です。上述のように、活動中はサポーターでいることに徹してください。
静かに見守ったり、困っているペアにそっと声をかけたりすることで、学習者は安心して取り組めます。
三つ目は振り返りとまとめの時間を必ず作ることです。

ペアやグループ活動の後は、発表して全体で答えを共有したり、「どうでしたか?」と感想を聞いたりする時間を作ると、学習が整理され、達成感も高まります。
盛り上がる授業は偶然ではなく、こうした小さな工夫の積み重ねから生まれます。
まずは
「簡単にする」
「教師が出しゃばらない」
「まとめの時間を作る」
ことを意識してみてください。
それだけで参加型授業はぐっと成功に近づきます。
5. 授業後に振り返って次につなげる方法
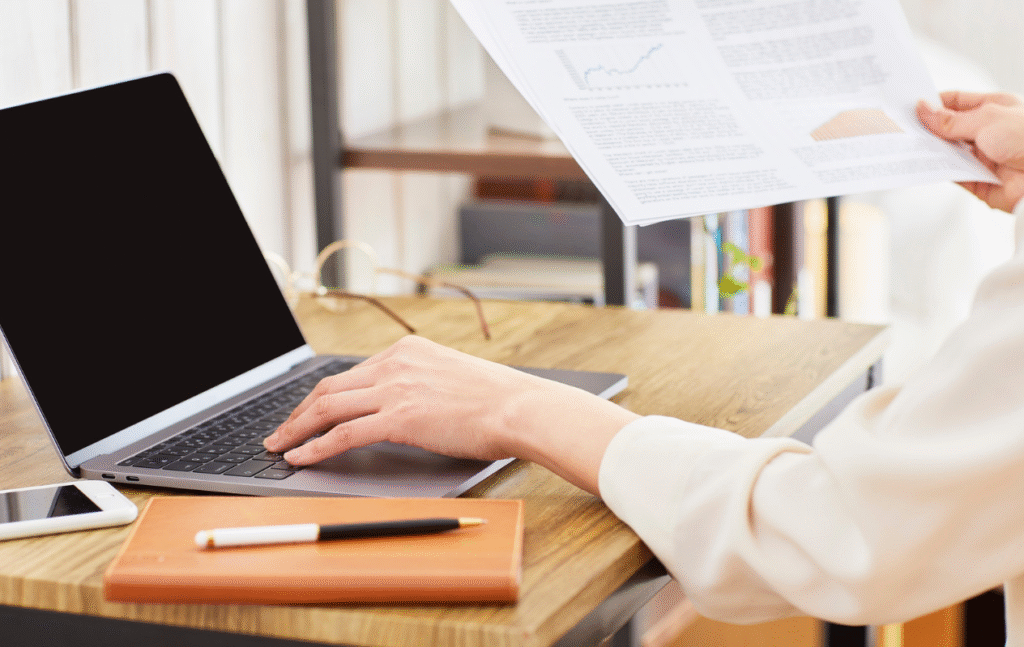
授業が終わると「ふぅ、なんとか終わった!」とホッとして、そのままにしてしまいがちになります。

何コマも続けて授業をこなした後は、とても疲れますよね。
でも、振り返りをしないと、同じ失敗を繰り返したり、せっかくの工夫が次に活かせなくなったりします。だから、授業の後に振り返りの時間を作ることを習慣にしましょう。
これは次の授業準備時間の短縮にも繋がります。
やり方はシンプルでOKです。
まずは「上手くいった活動」と「上手くいかなかった活動」をメモしましょう。
上手くいかなかった活動は、「どこでつまずいたか(教師or学習者)」「なぜ上手くいかなかったか」までメモできると完璧◎です。
また、活動のすぐあとに学習者の反応を聞くのも効果的です。
「今日の活動はどうでしたか?」「楽しかった?」「何が難しかった?」と一言問いかけてみるだけでも良いです。
学習者は割と正直に答えてくれることが多いので、自分では気づかなかった改善点に出会えることもあります。
最後に大切なのは、反省を「次回どうするか」に繋げること。
ただ、授業後にここまでやるのはかなりの負担になると思うので、これは次に同様の活動をするときでも良いと思います。
そのときのために、失敗したポイントや上手くいったポイントは、その日のうちに細かくメモしておきましょう。
単に「失敗した」で終わらせず、「次はペアじゃなくてグループにしよう」「説明をもっと短くしよう」と行動に落とし込める仕組みを作っておくのがポイントです。
授業後の数分の振り返りが、次の授業を大きく変えていきます。
まとめ
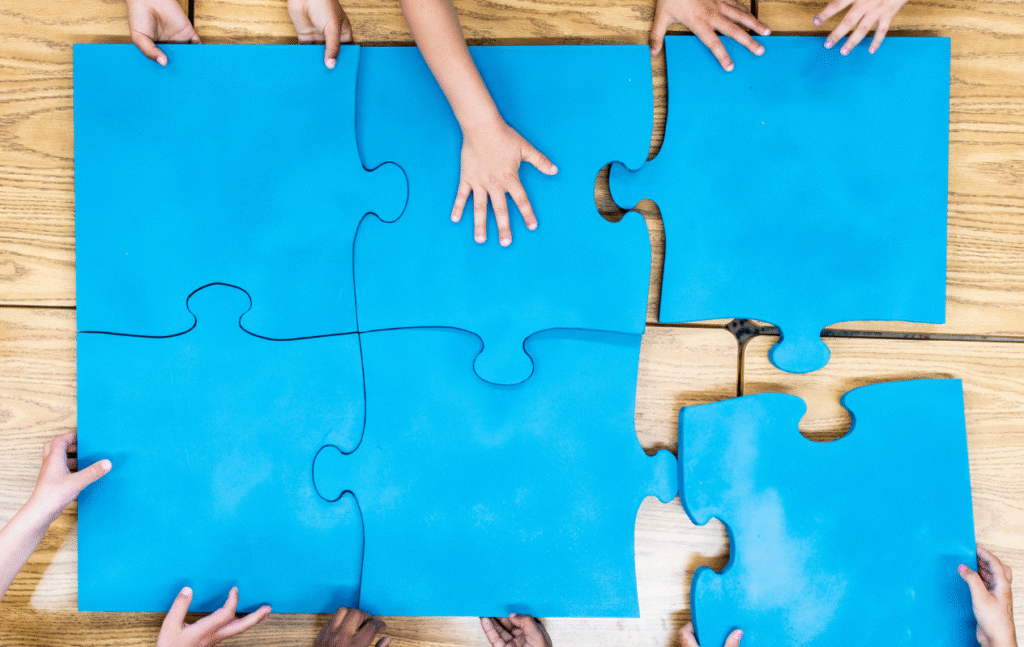
いかがでしたか。
今回の内容をまとめておきます。
・大切なのは実際に日本語を使ってみること
・説明は短く、体験は長く
・小さな成功体験を積み重ねられるようにする
・全員が関われる仕組みをつくる
・正解より挑戦を評価する
・教師はサポーターに徹する
・まとめの時間を作る
・授業後に振り返りを行い、次に繋がる仕組みを作る
新人時代は試行錯誤の連続ですが、その一歩一歩が教師としての土台となります。
完璧を目指さず、学習者と一緒に成長していってください。
それが参加型授業の1番の魅力であり、あなたが教師を続けていく力にもなると思います。
ー
新人日本語教師におすすめの本はこちら↓
日本語教師×ICTに特化した本はこちら↓
ー
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
この記事が参考になった!と思ったら、SNS等でシェアしてもらえると嬉しいです。
これからもよろしくお願いします。
X(旧Twitter)のフォローはこちらから
下のコメント欄からコメントを投稿される際は、免責事項及びプライバシーポリシーをご確認ください。
コメントの送信を以って、記載内容に同意したものとみなされます。

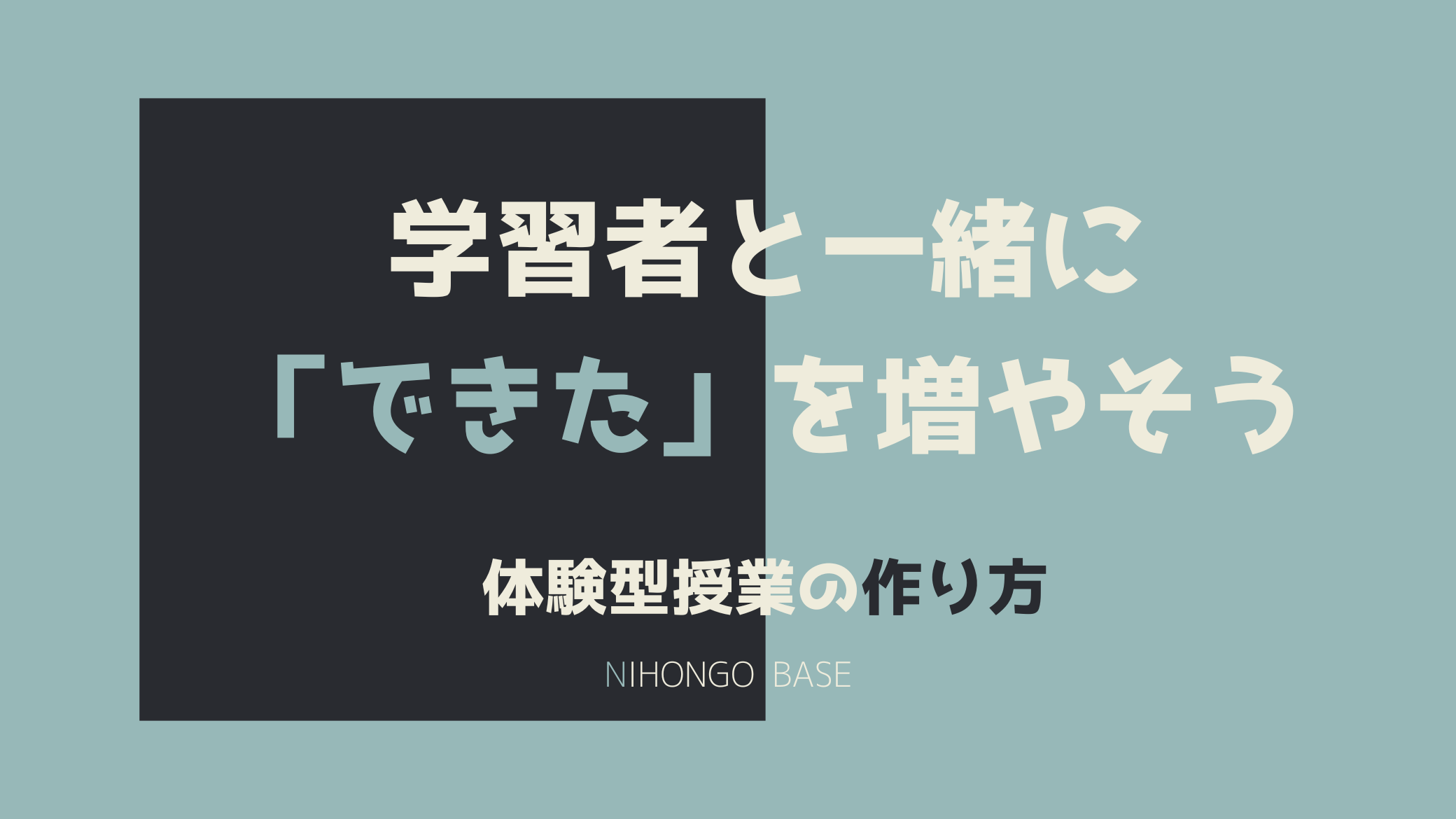

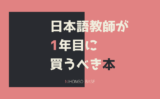
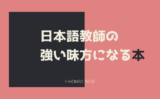

コメント